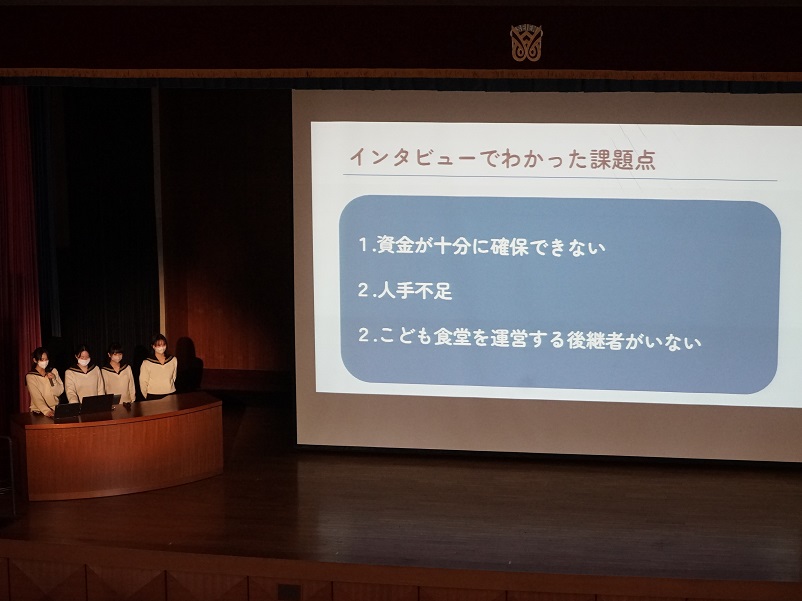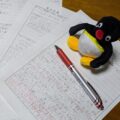昨日に引き続き、4月19日の全校講堂朝会に対する生徒の感想をお届けします。今日は、学年ごとにまとめます。中1は中1なりに、中2は中2なりに、そして高校生は高校生なりに…みんな自分の土台を確かめ、今を想い、未来を考えています。
中学1年生の想い
入学式からまだ2週間足らずで、最初の講堂朝会に臨んだ中学1年生。西遠ってどんなところなの?と疑問いっぱいな中でいろいろ考えたあとが、そして西遠生として頑張ろうという決意が、集会記録の中にあふれていました。
◎私たち西遠生が未来を拓く女性になるためには、いろいろな人とのかかわりが大切なのだと知りました。友達や家族、先生方や地域の方々のお話を聞いたり、関わったりしていくことで、私たちがよりよい女性になるためのことが身につくのだと思います。
◎西遠で身につけたい力について、身につける理由や、身につけるために西遠ではどんな活動をしているのか、どのイベントや活動がそれに該当するのかがよく分かりました。これからの西遠での活動について、やることの理由が今回分かったので、よりいっそう身が入るなと思いました。
◎1年生の一週間の学習目標時間は20時間。平日は2時間で、休日は5時間勉強すると達成できる時間。これだけでもかなりきつめのスケジュールなのに、さらに高校3年生はこれにプラスして15時間あると考えると、本当にすごいなと思いました。部活も勉強も両立して毎日を過ごしている先輩方を尊敬すると共に、自分もそんな人になりたいと思いました。姉妹ピア活動などで関わることのできる先輩たちからたくさんのことを学んでいきたいです。
中学2年生の想い
この春、初めて「先輩」の立場になって中学2年生たち。1年前を振り返りながら、土台を確認し、前進しようとしている、そんな前向きな気持ちが伝わってきます。
◎今年度初の講堂朝会でのお話を聞いて、2年生になったという自覚と責任を持った行動を心がけたいと思いました。今までは、「まだ1年生だから」と言ってもらえることが多くありました。けれど、2年生に進級したということは、自分中心の行動はなるべく控えて、先輩、後輩を支えるという役割を精一杯頑張ろうと思います。三年生の先輩方は学力判定テストなどで多忙だと思うので、先輩方を補佐して、また一年生は私たちもそうだったようにまだ慣れない学園生活だと思うので、困っていたら優しく声をかけられる立場が理想です。まだ一年生の記憶が新しい私たちだからこそ分かることもあるのではないかなと思います。私自身も困っていたとき先輩に質問をしたら丁寧に教えてもらったり、様子を見て先に声をかけていただいたときもありました。そんな先輩は、今でも私たちの中のあこがれの存在です。先輩方のようにはできなくても、少しでも力になれるような努力をしたいです。また、同級生の間でも協力することを大切にしたいです。
◎西遠に入って1年が経ちました。この講堂朝会で、自分がどんな西遠生になるべきか改めて復習できました。未来を拓く学びのデザインで学んだことは、一人で抱え込んで問題を解決しようとするのではなく、周りのたくさんの人に相談し、協力しながら解決していくことが大切だと思いました。私は小さい頃から今も、ずっと数え切れないぐらいに父と母に相談しながら乗り越えてきました。今までやってきたことがあっていたと思って、これからも続けたいです。
中学3年生の想い
中学の最上級生としての決意、学力判定試験(8月)への心構えなど、中学3年生の心も熱いです。
◎確かな学力を身につけるためには、「言葉」が必要不可欠だと改めて感じました。私は、言葉について考えるときいつも南直哉さんの言葉を思い浮かべます。「自分の感情に意味を与えるためには、器 すなわち言葉が必要」なのだと。私は、国語が苦手です。自分たちが毎日使っている言葉で、問題に必ず答えが書かれているから一番簡単だよ、と母に言われながらも思うように点数が伸びません。私の今年の目標は、学力判定試験に一発合格することです。苦手な教科を克服するために、私は国語の学習時間を増やしました。3年生になって、国語の宿題もたくさん出るので問題を解く時間を決めて集中して取り組むようにしたら、だんだんと問題文を読むことが楽しみになってきて、楽しく問題に取り組めるようになりました。社会に出ていちばん重要なことは、国語(言語)なのでその日に出された宿題をきちんと取り組み、提出日にしっかり出したいです。また、西遠には大きな図書館があります。私は、図書館をあまり利用していません。高校生になると本を読める時間が少なくなると聞いたので、今年一年は学判に向けてもしっかり本を読む時間を確保して、読解力を高めたいです。
◎人前で発表したり、自分のことを話したりしないと言葉は上達しないだろうと思いました。西遠では人前に出ることが多く、何かを小学生に説明したり、地域の人達と交流を深めることが多いです。その場面を使って私は言葉をもっと上達させ、人と語り合えるようになりたいなと思いました。
高校1年生の想い
高校からの入学生もまた、未知の世界に足を踏み入れ、不安もあったことと思いますが、同級生と共に頑張ろうとする気持ちをもらいました。また、西遠の中学から進んだ生徒からは、1級上の先輩たちに協力しようという威容を感じました。
◎今日は西遠女子学園に入学して初めての土曜日の全校講堂朝会でした。校長先生の話を聞いて、初めて聞く言葉がありました。それはコンピテンシーという言葉です。この言葉は、良い成果を出す人の共通する行動や、能力のことをいいます。私はこの言葉をきいて私達が目指している未来を拓く女性になるために必要な「確かな学力」「世界で生きる力」「豊かな人間性」にすごくあっていると思いました。私達が未来を拓く女性になるために必要なことが一つの言葉でまとめられることを初めて知ったので、意味を知ったときには少し驚きました。また、この3つの要素に共通して必要なことは「言葉」だということを聞き、私は言葉を持つことの大切さをあらためて感じました。またこれからは、言葉があることに感謝して短い単語などでまとめてしまわずに、多くの言葉をつかって行きたいと思いました。
◎生徒会活動では、何事にも全力で取り組みたいですが、やはり自分事として捉えることが一番大切だと思いました。来年度は120周年なので、それに向けて今年度、先輩方が動き出そうとしています。先輩方のサポートをして、来年度の活動に活かしていきたいです。
高校2年生の想い
学園の中心学年になった高校2年生たち、時の流れの速さに驚きつつも、責任感を胸に歩み出しています。
◎校長先生のお話を聞いて、一番衝撃を受けたのは、もう五年生になってしまったという事実です。お話の中で何回か「高校生」「二年生以上」などなど、私が五年生になったという事実を自覚する言葉がありました。そのような言葉を聞くたびに、中学生だった頃はこんなことを思ってたなと思い出すと同時に、あと一年で六年生という事実に驚いていました。西遠に入学してからの4年間は本当にあっという間で、一瞬で四年が経ってしまいました。私の中の時計は未だ高校一年を指しています。毎年のように講堂朝会で勉強しなさいと言われ続けはや4,5年。やっとスマホから離れ、勉強するようになりました。私もこの西遠で成長することができました。
◎姉妹ピア活動は今まで先輩か後輩と楽しく話すことができたらいいなと思って、参加していましたが、今年は6年生に次ぎ、2番目の長老で、6年生の下、下の学年を連れていかなければならないと気づきました。1,2年生とは行事の目指す目標や意味が変わり、大きくなるにつれ、それらに責任も加わり、とても面白いものであるが、かえって後輩にその姿を見られるので、慎重にかつ、5年生としてのプライドを持たなければならないと気づきました。学園祭を運営していく中心学年は私たち5年生です。私たちの学年で務まるかとても不安です。4年生のとき、初めて学園祭実行委員に挑戦しました。その時お世話になった5年生は、厳しかったですが、学園祭を盛り上げ、来てくれた人が迷うことなく、色々なことを工夫し、実行に移していました。先輩方はすごかったんだなと偉大さに気づきます。その学年があっという間にやってきてしまいました。楽しみである反面不安もあります。今までの生活で培ってきた経験や学んできたことは、少しでも役に立つと思います。そのことを信じて、発足まで自分を磨き続けようと思いました。
高校3年生の想い
高校3年生の感想には、今までの足跡を振り返ったうえで、学園生活の総まとめに取り掛かるという気概に満ちたものが多くありました。ぜひ下級生に読んでほしい感想ばかりです。
◎戦後80年目の今年、高校生になって三度目の慰霊式にどう挑むかを深く考えることができました。去年の九州研修旅行は、これまでの平和学習の集大成だと感じました。長崎での市内研修、記念公園や原爆資料館での平和学習、活水高校の方との平和交流など、様々な場面で平和について触れることができました。静岡県に留まらず、実際に被爆をした県に行くことができた九州研修旅行の後だからこそ、慰霊式で平和とはなにかを更に深く考えることができるだろうと思いました。この話を聞いて、改めて今までの平和学習や研修旅行での出来事について追求することができ、今年の慰霊式にどう挑むか何を思いながら式に出るかを考えることができました。
◎今回のお話の中でとても印象に残っていることの一つが、西遠生としての総合探究知であるコンピテンシーです。今回六年生になってこの力がついてきているのか考え直してみました。21世紀型スキルなどは、HR展の責任者を4年生のときにやってスキル一つ一つの項目のことを親身に考え、行動に移せるよう努力した思い出があります。そのときに培った力は、昨年の5年生のHR展にてフォロワーシップを重視し役立つことができました。そして今年、6年生になって体育大会で実行委員長を務めています。チーム編成や団長を置くことなど一から作り上げていくことが多く、忙しいですが、実行委員としての仕事がないと行事が成り立たなくなるということをとても実感しています。これまでは何気なく参加していた体育大会でもたくさんの人の時間と労力と努力によって作り上げられていると思うと、どの行事にもかかわらず日常の講堂朝会や土曜プログラムにもっと積極的に毎度真剣に取り組みたいと思いました。そして今年は姉妹リーダーも務めます。後輩との関わりがこれまで少なかったので、はじめはどう接していいか分からず後輩に話しかけられずにいました。しかし姉妹掃除や姉妹交流会などをしていくうちに名前や趣味などを聞いて話をするようになりました。他にも掃除の仕方がわからない一年生に教えたり、後輩に時間を見て指示を出し、15分間しっかりと掃除に取り組めるようにリーダーとして頑張っています。
◎私はこれまで女性の生き方作文の代表をしたり、学園祭実行委員長を務めたり、国際カンファレンスや探究フェスタに出場したりするなど、人前に立って意見を述べる場に何度も立たされてきました。それらの活動の中で、批判的思考や、問題解決、地域とグローバルの良い市民である、といった21世紀型スキルを身につけてきたと思います。まだまだ未熟な部分のほうが多いですが、それらの経験が私を大いに成長させてくれたことは確かだと感じています。
◎私はこの5年間さまざまな機会で21世紀型スキルを身に着けてきた。今回の講堂朝会の日、私は次の時間の公開LHRの担当だった。いつものLHRよりも多く事前情報を調べ、メンバーとより深く話し合いをした。「このサイトは事実より個人の主張が強いので、みんなに見せるスライドに載せないほうが良い」など、細かく情報源についても考えた。21世紀型スキルである情報・ICTリテラシーはもちろん、批判的思考などの思考の方法も、これを通して随分鍛えることができた。社会に出てもこのスキルは役に立つので、推薦で選ばれたときは少し嫌だったが、とても良い機会になった。
以上、6学年にわたっての講堂朝会の感想を紹介しました。
こうした自信や決意を持って歩み始めた生徒たちの今年一年の成長がますます楽しみになってきました!