夏休み、ついつい本よりも他の方へと興味関心が行きがちです。反省。
最近読んだ本を、久々に挙げます。
「1945 最後の秘密」三浦英之著
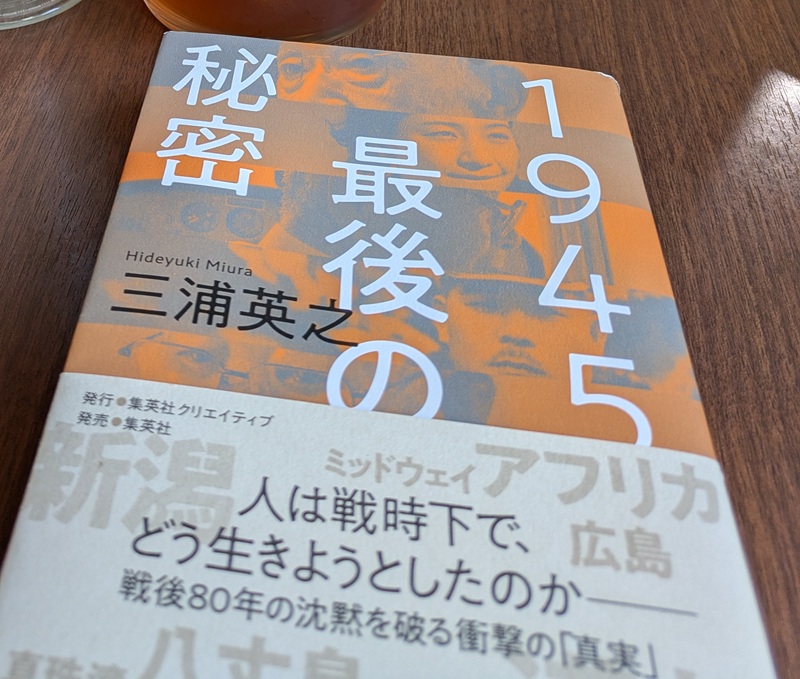
1945年終戦の年に、どんなことが起きていたのか。長い沈黙を破って著者に手記を送った方、丹念な著者の取材で明らかになった事実。この本には、朝日新聞記者の三浦英之さんの「戦争」「歴史」に向き合おうとする真摯な姿勢が、新たな真実を世の中に送り出した、その内容と軌跡が描かれています。「南三陸日記」「五色の虹」など、今まで彼の本は何冊か読みましたが、その文章力には人を愛する気持ち、大事に思う気持ちがあるのだといつも確信します。今回、この本はどうしても8月に読み終えたかった。戦争について、平和について、8月は深く考えるべき月であるから。もちろん、8月だけ考えればいいんじゃないけれども、今年の夏は、この本と向き合うことにしました。
新潟の原爆疎開、日本軍のマダガスカル攻撃、終戦間際に八丈島で行われていたことなど、この本で初めて知った史実もたくさんありました。
「五色の虹」出版の際のエピソードも、彼の痛恨の後悔も、この本を読んで知りました。「五色の虹」は、今は亡き父も読み、二人で感想を語り合った思い出があります。あの時の取材がその後も続き、今回、100歳を超えた先輩新聞記者の手記の公開秘話へとつながったのでした。101歳のその方は、手記を後輩である三浦氏に残し、亡くなりました。そのバトンタッチの鮮やかさにも、ぐっと胸をつかまれました。
今回も「継承」という言葉が、私の中で大きく刻まれました。戦争を知らない世代の「第一世代」として何をすべきか。また大きな宿題をもらいました。
「短歌研究 2025年9+10月号」
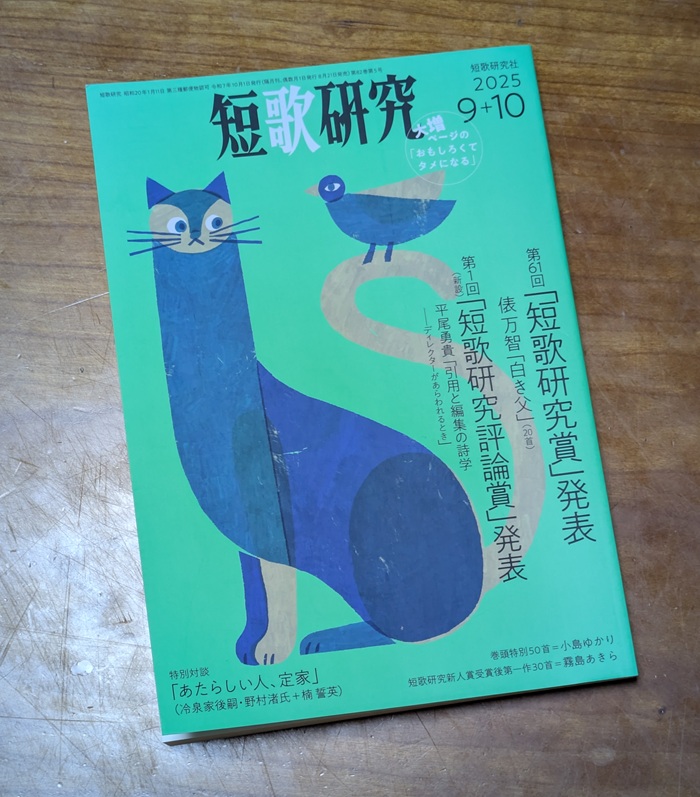
今回は、「短歌研究賞」発表号。
第61回短歌研究賞は、俵万智さんの「白き父」が受賞しました。「白き父」は、「短歌研究2024年5・6月号」に掲載されていたもので、お父様の死をテーマにした短歌群が心に残っていたので、この作品が受賞したということを知った時には、嬉しかったです。改めて、今号のページをめくり、「白き父」を再読しました。そして、受賞者俵さんの言葉も読み、親の最期に向き合うことについて考えさせられました。お父様が危ないというとき、仕事をキャンセルしようかと考えた俵さんに「その選択を、お父様が喜ぶかどうかを考えてみては?」というお医者様の言葉。これには、はっとさせられました。この一言に出会えたことも今回の大きな収穫だでした。
我よりも我の短歌を暗誦しその短歌ごと消えてしまえり
父往きて初めての雪 思い出し泣きという語の辞書にはあらず
大谷が結婚しても藤井くん負けても真顔のまんまの遺影
音楽が世界に色を付けてゆくことを知る朝、水をやらねば 俵万智「白き父」より
☆ ☆ ☆
読書感想文の請負人とか、AIに書かせることの是非など、なんだか「宿題」って何なんだろうと考えさせられるニュースが次々舞い込んできます。自分で本を読んで、自分自身の感想を、不器用でもまとめることこそ大切です。その文章が下手だったとしても、その本の意味が分からなかったとしても、本の感想は本と自分との対話なのです。教員が感想文の拙いところを指導したりはしますが、それはその人に考え方や表現の仕方のヒントを与えることであり、けなしたり否定したりするものではないので、今、感想文を書くことで頭を痛めている人がいたら、ぜひ素直に綴ること、自分と向き合うことをお勧めします。


